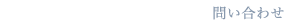一
1 相手に配偶者がいて、そのことを認識しつつ、不貞行為に及んだ不貞相手は、配偶者から慰謝料請求をされる法的立場となります。
自分の配偶者が、不貞していたという場合、配偶者がいることを不貞相手が認識していたのであれば、その不貞相手に慰謝料請求したいと思うのは、自然のことと言えます。
このように、自分の配偶者と不貞行為をしたことを理由に請求する慰謝料のことを、「不貞慰謝料」といいます。
2 不貞が判明した後、婚姻関係を継続する夫婦もいれば、離婚をする夫婦もいます。
不貞の結果、婚姻関係が破綻し、離婚に至った場合の慰謝料を「離婚慰謝料」といいます。
3 不貞慰謝料や離婚慰謝料の具体的金額は、個別事情により変動するので、明確な金額については、一般的には言えません。
しかし、離婚慰謝料の場合、不貞されて精神的苦痛を受けるだけでなく、離婚という被害も発生しているわけですから、離婚という結果が出ていない不貞慰謝料に比べて、金額は相当高額になると考えられます。
二
1 配偶者が不貞をして、離婚に至った場合、その配偶者に対して離婚慰謝料を請求することができます。
不貞をした配偶者は、離婚について直接的な責任を負うわけですから、不貞だけでなく離婚慰謝料についても支払うべき義務があります。
2 では、不貞された配偶者は、離婚慰謝料についても、不貞相手に対して請求することができるのでしょうか。
この点が問題となった最高裁判所平成31年2月19日判決について、ご紹介いたします。
三
1 事案としては、上司の既婚男性Aと部下の女性Bの社内不倫でした(以下「本件不貞」といいます)
2 Aの妻であるXは、本件不貞を契機に、Aと離婚することを決意し、調停離婚をしました。
Aとしては、自分が離婚の直接的原因を作ったわけですから、Xに対して離婚慰謝料を支払うべきことになります。
3 本件において、Xは、不貞相手であるBに対しても、離婚慰謝料として、不貞慰謝料よりも高額の慰謝料を請求しました。
Aの責任とBの責任を同等と考えることができるかが、問題となったのです。
四
1 この点、最高裁は、離婚は、本来、当該夫婦の間で決められる事柄であるという点を重視しました。
そして、Xの配偶者であるAと、第三者であるBの責任を同等に解することはできないという認識を示しました。
2 つまり、Xは、配偶者であるAの場合と異なり、不貞相手Bに対しては、当該夫婦を離婚させたことを理由とする離婚慰謝料までは請求できないのが原則であるという判断をしました。
配偶者がいることを認識した上で不貞をした不貞相手は、離婚慰謝料までは負担しなくて良いという原則になります。
3 なお、最高裁は、例外的に、不貞相手が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして、当該夫婦を離婚せざるを得ない状況に陥れたと評価すべき特段の事情がある場合には、不貞相手に離婚慰謝料を請求できるとしています。
もっとも、この最高裁のいう例外に該当するのは、大変特異な場合に限られ、現実的に想定することは難しいのではないかと思います。
五
1 本来、共同不法行為の場合、共同不法行為者は、発生した損害について、連帯して賠償責任を負います(民法719条1項)。
本件の場合、AとBが共同して、不貞行為という不法行為をし、その結果Xに対し、離婚という損害を発生させているわけですから、Xの離婚慰謝料についても、Bが連帯して損害賠償義務を負うのが論理的のようにも思います。
2 しかし、家庭の事件である離婚という特殊性、本来夫婦間で協議し決定される事柄であるという点から、一般の民法のロジックとは離れて、軌道修正をしたものと思われます。
3 離婚のような家庭に関する人事事件は、ビジネス取引とは異なり、当事者の意思や人的関係性が重視されます。
この事例でも、Xの配偶者であり離婚の当事者でもあるAの責任と、第三者的立場で不貞をしたBの責任とを同列に扱うことはできないという価値判断があったのだと考えられます。
4 とはいえ、不貞慰謝料だからといって、常に低額という訳ではありません。
不貞行為の個別事情や経緯によっては、不貞慰謝料といえども、相応の慰謝料額が認められる可能性もあると言えます。