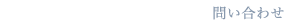一
1 詐害行為取消は、裁判所に請求するものであり、その効果は、詐害行為取消判決の確定により発生します。
2 では、この詐害行為取消の効果が、判決確定後の将来に向かってのみ発生するのでしょうか。それとも、取り消しの効果が、判決確定前の過去に遡って発生することになるのでしょうか。
この点は、受益者の取消債権者に対する受領金支払い債務の履行期がいつなのかという問題にリンクして、問題となります。
なぜならば、仮に、詐害行為取消の効果が将来に向かってのみ発生するとした場合、詐害行為取消判決の確定前に、受益者の受領金支払い債務の弁済期が来ることはあり得ず、履行遅滞になることはないという結論になるからです。
二
1 この点、最高裁判所は、詐害行為取消権の制度趣旨に立ち返って、判断をしました。
2 そもそも、詐害行為取消権は、詐害行為を取り消した上で、逸出した財産を債務者の一般財産に回復して、債務者の財産を保全し、債権者が債権回収できるようにするための制度です。
受益者は、詐害行為によって債務者の一般財産を逸出させた責任があるので、受益した財産を債務者に回復させる義務を負うことになります。
3 このような詐害行為取消権の制度趣旨に鑑みれば、詐害行為取消の効果は、過去に遡って効力を生じるとするのが相当であると最高裁判所は判断しました。
したがって、取消判決前であっても、受益者が財産を受領した時点で、受益者に受領金支払い債務が発生することになります。
4 詐害行為取消の効果が過去に遡らない(将来効のみ生じる)とすると、受益者としては、詐害行為取消判決確定までの間、詐害行為による受益財産を運用して運用利益を取得することができることになります。
詐害行為による財産の運用益を受益者が取得できるというのはアンフェアであるという考え方が、最高裁判所のバックグラウンドにありました。
三
1 このように、詐害行為取消判決の確定により、取り消しの効力は過去に遡るので、受益者の受益金支払い債務は、財産を取得した時点で既に発生していることになります。
2 そして、この受益者の受益金支払い債務は、期限の定めがない債務に当たるので、履行の請求を受けた時点で弁済期が到来し、それ以降履行遅滞になります(民法412条3項)。
3 そこで、一般的には、詐害行為取消訴訟の訴状の送達をもって履行の請求があったと考え、その翌日から受益者の受益金支払い債務は履行遅滞になるので、その日を起算点として遅延損害金が発生するのです。
以上