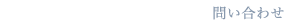一 交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、その賠償額や支払方法について、
複雑な問題が生じます。
以下、実例をカスタマイズして述べます。
二
1 4歳のXが、大型貨物自動車に衝突されて脳挫傷等の傷害を負い、後遺障害等級3級相当の高次脳機能障害等の後遺障害が残ってしまいました。
2 Xの両親は、当該自動車の運転手を被告として、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。
また、Xの両親は、自動車損害賠償保障法3条に基づき、当該自動車を保有していた会社も被告として、損害賠償請求をしました。
さらに、当該会社と対人賠償責任保険契約を締結していた保険会社も被告にして、損害賠償請求をしました(当該保険契約に基づき、当該運転手または当該会社に対する判決の確定を条件とする損害賠償請求をしました)。
三
1 まず、後遺障害の逸失利益を算出する際に、どの時点での賃金センサスを基礎収入とするか、という点が争点になりました。
2 この点、裁判所は、Xの症状固定の時点の年の賃金センサス平均賃金を、基礎収入の金額にすると判断しました。
四
1 被告らは、本件事故当時は、Xの後遺障害の程度は3級相当であったが、子どもの頭部外傷による後遺障害は、脳の成長過程で機能が回復するものであり、今後も状態の改善が期待できるから、後遺障害等級5級相当であると主張しました。
2 しかし、Xは、4歳で本件交通事故に遭遇し、その後小学校・中学校は特別支援学級に在籍し、その後も高等支援学校に進学していました。
裁判所は、このような客観的状況に鑑み、後遺障害の程度が、5級相当まで改善したと評価できないと判断しました。
五
1 なお、民法772条2項は、損害賠償の額を定めるにあたって、被害者の過失を考慮することができると定めています(いわゆる過失相殺)。
Xは、本件事故時に4歳であり、過失相殺能力のない幼児ですが、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者に過失があれば、過失相殺の対象になります(いわゆる被害者側の過失の理論)。
被害者本人を保護者が十分に看視・監督していなかったような場合には、過失相殺の対象となり得ます。
六
次に、賠償金の支払い方法について、定期金賠償が認められるかが問題となります。
1 将来の介護費用については、問題なく定期金賠償の方法が認められます。
2 では、後遺障害逸失利益についても、定期金賠償が認められるのでしょうか。
この点、Xの年齢や後遺障害の性質・程度、介護状況などに照らすと、Xの後遺障害逸失利益については、将来の事情変更の可能性が比較的高いと考えられます。
後遺障害や賃金水準の変化に柔軟に対応できるという定期金賠償の特質が妥当するケースと考えられ、かつ、Xの両親も定期金賠償の方法を強く望んでいました。
したがって、後遺障害逸失利益についても、定期金賠償を認めると裁判所は判断したのです。
このように考えたとしても、いずれにせよ将来の介護費用については定期金賠償が認められる以上、あわせて後遺障害逸失利益について定期金賠償を認めても、今後の被告らの損害賠償金支払いの管理等について、特段過重な負担をかけるわけではありません。
3 なお、将来の介護費用は、被害者が死亡するまで、定期金賠償となります。
しかし、後遺障害逸失利益については、被害者が67歳になるまでの間について認められることになります。
つまり、67歳まで働いて収入を得られたであろうという前提のもと、その間収入が得られなかった不利益を賠償するのが、後遺障害逸失利益なので、67歳という終期が設定されているのです。