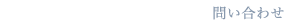一
遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、その他一切の事情を考慮して決定されます。
現金や預貯金は、性質上分割しやすいといえますが、同族会社における株式の場合、特別の配慮が必要です。
この点について、実例をカスタマイズしてお話いたします。
二
1 A社は、建築工事の請負施工等を事業とする株式会社であり、その代表取締役Bは、A社の発行済み株式すべてを保有していました。
A社は、Bの祖父、父が歴代の社長を務めた、従業員も6名だけの非公開会社であり、株式の譲渡制限もある同族会社でした。
2 Bが遺言を残さずに死亡し、子どもであるX及びYがBの遺産を相続しました。
ここで問題となるのは、Bが保有していたA社の株式をどのように分割するか、という点です。
3 つまり、Xは、Bの生前からA社で働いており、次のA社の代表取締役になる予定でした。
一方、Yは、A社とは関係のない別の仕事をしており、A社の経営に関与していませんでした。
4 理屈上は、XとY社が、法定相続割合でA社の株式を相続するようにもみえます。
しかし、XとYは、従来から不仲だったという事情がありました。
このままでは、XがA社の代表取締役に就任したとしても、Yが株主として難癖をつけてくる可能性や、スムーズに株主総会決議ができないというリスクがありました。
三
1 そもそも、A社のような小規模の同族会社の場合、安定した経営をしていくためには、株式が分散し多数の株主が発生するという事態を避ける必要があります。
実際に会社を経営する人が、会社の株主になることにより、スムーズな株主総会決議も可能になるし、経営が円滑に進みます。
2 その意味で、次のA社の代表取締役になるXが、Bが保有していたA社の株式全部を相続するという形が、A社の安定した経営にとって望ましいといえます。
また、Yとしては、もともとA社とは無関係の仕事をしていて、A社の経営に関与したことも無ければその気もありませんでした。
つまり、Yとしては、本来相続するはずだったA社の株式の株式価格相当のお金を取得できれば良いのであって、あえてYにA社の株式そのものを相続させなければならない必要性はありません。
3 そこで、裁判所は、Xが、Bの保有していたA社の株式全部を取得し、その代わりに、XがYに対して、Yが取得するはずだった株式の価格相当の代償金を支払うという審判をしたのです。
このような遺産分割をすることによって、株式の細分化、分散を避け、会社経営が安定します。
そして、Yに対して株式の価格相当の代償金が支払われることにより、バランスも維持でき、フェアな解決になります。
四
1 なお、このような裁判所の審判を求めるためには、Xが、Yに支払うべき代償金額の支払い能力を立証する必要があります。
具体的には、代償金額を超える預貯金を持っていることを、通帳の記載や残高証明書などにより証明することになります。
裁判所としても、Xがきちんと代償金を支払う経済力があることを確認できないのに、XがA社の株式全部の相続を認めることはありません(代償金が確実に支払われることが担保されていることが、代償分割の前提です)。
2 このように、Xが、Yに支払うべき代償金を十分保有していない場合には、原則通り、A社の株式そのものを分割して取得する結論になります。
3 もっとも、Bの遺産として、他に預貯金や有価証券など換金できる財産があれば、それを多くYに取得させることによって、代償金に充当することも考えられます。